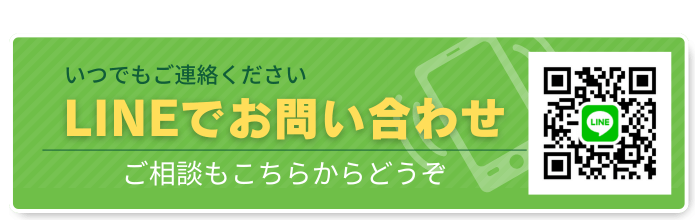過敏性腸症候群(IBS)でお悩みですか? 腹痛、下痢、便秘など、つらい症状に悩まされ、日常生活に支障をきたしていませんか?
この記事では、IBSの症状・原因・治療法から、日常生活でできる具体的な改善策までを網羅的に解説します。
IBSのメカニズム、病院での診断方法、薬物療法や食事療法、ストレス対策、漢方など、様々な角度からIBSへの理解を深め、あなたに合った対処法を見つけるお手伝いをします。この記事を読み終える頃には、IBSの正しい知識を身につけ、症状緩和とより良い生活への一歩を踏み出せるはずです。
はじめに 過敏性腸症候群の基本知識
過敏性腸症候群(IBS)は、腹痛や腹部不快感を伴う慢性的な消化器疾患です。
すごく簡単に言うと、「生まれつきお腹が弱い+不適切な食事+ストレス」による消化不良です。
下痢や便秘、あるいはその両方を繰り返すことが特徴で、生活の質を著しく低下させる可能性があります。IBSは命に関わる病気ではありませんが、症状の重症度は人によって異なり、日常生活に大きな影響を与える場合があります。多くの場合、症状は長期にわたり、寛解と増悪を繰り返す傾向があります。
明確な原因は特定されていませんが、腸の運動異常、内臓知覚過敏、腸内細菌叢の乱れ、心理社会学的要因などが複雑に絡み合っていると考えられています。
近年では、低FODMAP食などの食事療法や、認知行動療法などの心理療法の効果が注目されています。
過敏性腸症候群とは何か?
過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome: IBS)は、器質的な異常がないにもかかわらず、腹痛や腹部不快感、排便習慣の変化(下痢、便秘、またはその両方)が慢性的に続く機能性消化管疾患です。
「器質的な異常がない=治る可能性がある」というところは安心材料です。
検査を行っても炎症や潰瘍などの異常は見つかりません。Rome Ⅳ基準と呼ばれる国際的な診断基準に基づいて診断されます。
IBSは大きく分けて、下痢型(IBS-D)、便秘型(IBS-C)、混合型(IBS-M)、分類不能型(IBS-U)の4つのサブタイプに分類されます。それぞれのサブタイプによって症状や治療アプローチが異なります。
過敏性腸症候群の有病率
過敏性腸症候群は世界的に見ても一般的な疾患であり、人口の約10~15%がIBSを抱えていると推定されています[1]。日本国内においても、厚生労働省の調査によると、IBSの有病率は10%を超えると報告されています。
男女比で見ると、女性に多い傾向があります。また、年齢層別に見ると、20代から40代の若い世代に多く発症する傾向が見られます。ただし、どの年齢層でも発症する可能性があり、高齢者でもIBSと診断されるケースは少なくありません。
過敏性腸症候群と他の消化器疾患との違い
| 疾患名 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 過敏性腸症候群 (IBS) | 腹痛、腹部不快感、下痢、便秘 | 器質的異常なし、慢性的な経過 |
| 炎症性腸疾患 (IBD) | 腹痛、下痢、血便、発熱 | 炎症、潰瘍などの器質的異常あり |
| クローン病 | 腹痛、下痢、血便、発熱、体重減少 | 消化管全体に炎症が起こるIBDの一種 |
| 潰瘍性大腸炎 | 血便、下痢、腹痛 | 大腸に炎症が起こるIBDの一種 |
| 大腸がん | 血便、下痢、便秘、腹痛、体重減少 | 大腸に発生する悪性腫瘍 |
IBSは他の消化器疾患、特に炎症性腸疾患(IBD:クローン病や潰瘍性大腸炎)や大腸がんなどと症状が類似している場合があり、鑑別診断が大切です。
IBDは炎症や潰瘍といった器質的な異常を伴うのに対し、IBSでは器質的な異常は見られません。病気(壊れた)ではなく症候群(正常に動かない:機能障害)なので、日常生活の改善が非常に重要です。
また、大腸がんは進行するとIBSと似た症状が現れることがあるため、注意が必要です。腹痛や下痢、便秘などの症状が続く場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な検査を受けて下さい。[2]
症状と診断方法
過敏性腸症候群(IBS)は、腹痛や腹部不快感を伴う便通異常が慢性的に繰り返される病気です。検査をしても炎症や潰瘍などの異常が見つからないことが特徴です。
IBSの症状は多様で、個人差も大きいため、正確な診断のためには医師による問診や診察が不可欠です。
主要な症状とその特徴
IBSの主要な症状は、腹痛、腹部不快感、便通異常です。これらの症状は相互に関連しており、複雑に現れることがあります。
腹痛と腹部不快感
IBSの腹痛は、下腹部を中心に、キリキリとした痛み、鈍痛、張りなどの様々な形で現れます。排便によって痛みが軽減されることも特徴です。また、腹部膨満感やガスによる不快感を伴う場合もあります。
便通異常
IBSの便通異常は、便秘型、下痢型、混合型の3つのタイプに分類されます。
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 便秘型 | 硬い便や兎糞状の便が出にくく、残便感がある。排便回数が少ない。 |
| 下痢型 | 軟便や水様便が頻繁に出る。 urgency(便意切迫感)を伴うこともある。 |
| 混合型 | 便秘と下痢を繰り返す。 |
便の形状や排便回数、症状の持続期間などは個人差が大きく、同じタイプでも症状の程度は様々です。また、時間経過とともにタイプが変化することもあります。
その他、吐き気、食欲不振、倦怠感、頭痛、肩こり、腰痛、睡眠障害、不安感、抑うつなどの症状を伴う場合もあります。
診断プロセスと検査方法
IBSの診断は、Rome IV基準などの診断基準に基づいて行われます。
Rome IV基準
繰り返す腹痛が、最近3カ月の間で平均して少なくとも週1日あり、次のうち2つ以上の基準を満たす
①排便に関連する
②排便頻度の変化を伴う
③便形状(外観)の変化を伴う
※少なくとも診断の6カ月以上前に症状があり、最近3カ月間は基準を満たしていること
また、他の疾患を除外するために、血液検査、便検査、腹部X線検査、大腸内視鏡検査などが行われることもあります。
問診では、症状の出現時期、頻度、持続時間、誘因、緩和因子、便の状態、生活習慣、ストレスの有無などについて詳しく聞かれます。医師とのコミュニケーションを密にすることで、より正確な診断と適切な治療法の選択につながります。
原因とリスク要因
過敏性腸症候群(IBS)の明確な原因は未だ完全には解明されていませんが、様々な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
大きく分けて、原因は3つです。
- 生活習慣と腸内環境の変化
- ストレスと精神的影響
- 遺伝的要因
これらが複雑に関与していると考えられています。
生活習慣と腸内環境の変化
ほぼ普段の食事のことと考えてよいでしょう。
食生活の乱れや不規則な生活習慣は、腸内環境のバランスを崩し、IBSの症状を悪化させる可能性があります。具体的には、脂肪分の多い食事、食物繊維の不足、過剰なカフェイン摂取、アルコールの多飲などが挙げられます。
また、腸内細菌叢の乱れもIBSの発症に関与していると考えられています。
腸内細菌叢は、消化吸収や免疫機能に重要な役割を果たしていますが、食事の影響を強く受けます。バランスが崩れることで、腸の運動異常や炎症を引き起こし、IBSの症状につながる可能性があります。
食事とIBS
| 食品 | 影響 |
|---|---|
| 高FODMAP食 | 腸内で発酵しやすい食品は、ガス発生や腹部の不快感を引き起こす可能性があります。 |
| 脂肪分の多い食事 | 腸の運動を刺激し、下痢を引き起こす可能性があります。 |
| 食物繊維の不足 | 便の水分量が減り、便秘になりやすくなります。 |
| 刺激物(カフェイン、アルコール、香辛料など) | 腸を刺激し、症状を悪化させる可能性があります。 |
FODMAPについては、過敏性腸症候群(IBS)の改善に 低FODMAP食の進め方|田辺三菱製薬も参考になります。
腸内細菌とIBS
腸内細菌叢のバランスの乱れ(dysbiosis)は、IBSの症状に影響を与えると考えられています。
善玉菌の減少や悪玉菌の増加は、腸内環境を悪化させ、炎症や免疫反応の異常を引き起こす可能性があります。そのためプロバイオティクスやプレバイオティクスの摂取により、腸内細菌叢のバランスを整えることも有効でしょう。 腸内細菌とIBSの関係性に関する研究[3]も参考になります。
ストレスと精神的影響
ストレスは、IBSの症状を悪化させる大きな要因の一つです。
ストレスを感じると、自律神経のバランスが崩れ、腸の運動機能に影響を与えます。また、ストレスは腸内細菌叢のバランスにも影響を与え、炎症を引き起こす可能性があります。
ストレスと脳腸相関
脳と腸は密接に関連しており、「脳腸相関」と呼ばれています。
ストレスや不安などの精神的な状態は、腸の機能に影響を与え、IBSの症状を悪化させる可能性があります。逆に、腸の状態が悪化すると、精神的なストレスを感じやすくなることもあります。
認知行動療法などの心理療法は、ストレスを管理し、IBSの症状を改善するのに役立つでしょう。脳腸相関 | 健康用語の基礎知識 | ヤクルト中央研究所も参考になります。
過去のトラウマ
過去のトラウマ体験(虐待、いじめ、事故など)もIBSのリスク要因となる可能性が示唆されています。トラウマ体験は、ストレス反応システムに影響を与え、腸の機能異常を引き起こす可能性があります。
遺伝的要因
IBSは、遺伝的な要因も関与していると考えられています。家族にIBSの患者がいる場合、IBSを発症するリスクが高くなる可能性があります。しかし、特定の遺伝子がIBSの発症に直接関与しているかどうかはまだ解明されていません。
治療法と医療機関の選び方
過敏性腸症候群(IBS)の治療は、症状の緩和と生活の質の向上を目的として行われます。画一的な治療法はなく、個々の症状や生活状況に合わせて、医師と相談しながら最適な治療法を選択することが重要です。
大きく分けて、内科的治療、食事療法、生活習慣の改善、漢方治療・代替療法などが挙げられます。
医療機関を選ぶ際には、IBSの専門知識を持ち、患者さんの話を丁寧に聞いてくれる医師がいるかどうかが大切です。
内科的治療と薬物療法
IBSの薬物療法は、症状に合わせて選択されます。便秘型IBSには下剤、下痢型IBSには止瀉薬、腹痛には鎮痙剤などが処方されることがあります。
また、低用量抗うつ薬や抗不安薬が、腸の運動や知覚過敏を改善するために用いられる場合もあります。
近年では、IBSの病態に特化した新薬も開発されており、症状の改善に効果が期待されています。薬物療法は、あくまで対症療法であるため、根本的な解決には、生活習慣の改善や食事療法と並行して行うことが重要です。
主な薬物と作用
| 薬の種類 | 作用 | 使用上の注意 |
|---|---|---|
| ポリカルボフィルカルシウム | 便の水分を調節し、便秘と下痢の両方に効果 | 水分を十分に摂ること |
| ラモセトロン塩酸塩 | 下痢型IBSにおける腹痛や下痢を改善 | 便秘の副作用が現れる場合がある |
| トリメブチンマレイン酸塩 | 腸の運動を調整し、腹痛や腹部不快感を改善 | 眠気や口渇などの副作用が現れる場合がある |
上記の他にも様々な薬剤が存在します。詳しくは医師に相談してください。
食事療法と生活習慣の改善
IBSの症状は、食事内容や生活習慣に大きく影響されます。
高FODMAP食(発酵性の糖質を多く含む食品)は、腸内細菌によって発酵されやすく、ガス発生や腹部膨満感を引き起こす可能性があるため、摂取を控えることが推奨されます。過敏性腸症候群(IBS)における食事療法などを参考に、個々の症状に合わせた食事療法を実践することが大切です。
また、規則正しい食生活、適度な運動、十分な睡眠も症状の改善に繋がります。
高FODMAP食の例
- 果物:りんご、マンゴー、スイカなど
- 野菜:玉ねぎ、にんにく、ブロッコリーなど
- 乳製品:牛乳、ヨーグルトなど
- 甘味料:はちみつ、果糖ぶどう糖液糖など
漢方治療および代替療法の検討
西洋医学的な治療に加えて、漢方治療や鍼灸、アロマテラピーなどの代替療法も、IBSの症状緩和に役立つ場合があります。漢方薬は、体質や症状に合わせて処方され、消化機能の改善や自律神経のバランスを整える効果が期待されます。
ただし、これらの代替療法の効果には個人差があるため、医師や専門家と相談しながら慎重に検討することが重要です。過敏性腸症候群(IBS)の話 - 代官山パークサイドクリニックなども参考にしてください。
医療機関の選び方
IBSの治療を受ける医療機関を選ぶ際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。
- 消化器内科、またはIBSの専門外来があるか
- 患者の話を丁寧に聞き、症状や生活状況に合わせた治療方針を提案してくれる医師がいるか
- 必要に応じて、心理療法や栄養指導などのサポート体制が整っているか
- 通院しやすい場所にあるか
インターネット上の口コミサイトや病院のホームページなどを参考に、自分に合った医療機関を見つけることが大切です。
日常生活の改善策
過敏性腸症候群(IBS)の症状は、日常生活の改善策を実行することで大きく緩和される可能性があります。
食事、運動、ストレス管理、睡眠など、多角的なアプローチが重要です。自分に合った方法を見つけることが、IBSとの付き合い方を改善する鍵となります。
食事管理と運動習慣の見直し
低FODMAP食
FODMAPとは発酵性の糖質の総称で、小腸で吸収されにくく、大腸で発酵しやすい性質を持つため、IBSの症状を悪化させる可能性があります。
低FODMAP食は、これらの食品を制限することで症状の改善を目指す食事療法です。一時的にFODMAPの高い食品を避け、その後少しずつ摂取量を増やしていくことで、自分の体に合わない食品を特定できます。詳しくはコラム・記事/過敏性腸症候群(IBS)の改善に 低FODMAP食の進め方をご覧ください。
| 高FODMAP食品 | 低FODMAP食品 |
|---|---|
| 小麦、玉ねぎ、にんにく、りんご、牛乳 | 米、じゃがいも、人参、バナナ、アーモンドミルク |
食物繊維の摂取
食物繊維は、腸内環境を整える上で重要な役割を果たします。不溶性食物繊維は便のかさを増し、便秘の改善に役立ちます。水溶性食物繊維は便を柔らかくし、排便をスムーズにする効果があります。
ただし、食物繊維の摂取量を増やす際は、急激な変化を避け、水分を十分に摂るように心がけてください。IBSのタイプによっては、食物繊維の過剰摂取が症状を悪化させる場合もあるので、自分の体に合った摂取量を見つけることが大切です。
食物繊維に要注意!お腹が繊細な人は必見「FODMAP(フォドマップ)」 | サワイ健康推進課で食物繊維について詳しく知ることができます。
適度な運動
適度な運動は、腸の動きを活発にし、便秘の改善やストレス軽減に効果的です。
ウォーキング、ヨガ、ストレッチなど、無理のない範囲で体を動かす習慣を身につけましょう。激しい運動は逆効果になる場合もあるので、自分の体調に合わせて運動の種類や強度を調整することが重要です。
ストレス対策とリラクゼーション法
ストレスはIBSの症状を悪化させる大きな要因の一つです。ストレスを効果的に管理することは、IBSの症状改善に不可欠です。
リラクゼーション法の実践
ヨガ、瞑想、呼吸法、アロマテラピーなど、様々なリラクゼーション法があります。自分に合った方法を見つけて、日常生活に取り入れることで、ストレスを軽減し、心身のリラックスを促すことができます。
腹式呼吸は、手軽に行えるリラクゼーション法の一つです。深くゆっくりとした呼吸を繰り返すことで、副交感神経が優位になり、リラックス効果を高めることができます。
認知行動療法
認知行動療法は、思考パターンや行動パターンを変えることで、ストレスへの対処能力を高める心理療法です。IBSの症状悪化に繋がるネガティブな思考や行動を特定し、改善していくことで、症状の緩和に繋がることが期待できます。
睡眠と生活リズムの整え方
質の高い睡眠と規則正しい生活リズムは、自律神経のバランスを整え、IBSの症状改善に役立ちます。
睡眠時間の確保
毎日同じ時間に寝起きし、十分な睡眠時間を確保することで、体内時計が調整され、自律神経のバランスが整います。睡眠不足はストレスを増大させ、IBSの症状を悪化させる可能性があるので、質の高い睡眠を心がけましょう。
規則正しい生活リズム
食事の時間、睡眠時間、排便時間など、生活リズムを整えることは、自律神経のバランスを整える上で重要です。特に、朝食は体内時計をリセットする上で重要な役割を果たすため、毎日同じ時間に朝食を摂るように心がけましょう。規則正しい生活習慣を維持することで、IBSの症状をコントロールしやすくなります。
よくある質問
過敏性腸症候群(IBS)に関するよくある質問とその回答をまとめました。IBSの理解を深め、適切な対応策を見つけるためにお役立てください。
症状の緩和に効果があるのはなぜ?
IBSの症状緩和策は、主に腸の運動異常や過敏性を改善し、症状を引き起こす要因を軽減することに焦点を当てています。具体的には、以下のメカニズムが考えられます。
食事療法
低FODMAP食は、発酵しやすい糖質を制限することで、腸内でのガス発生や水分貯留を減らし、腹痛や膨満感を軽減します。食物繊維の適切な摂取も、便通を整えるのに役立ちます。
ストレス管理
ストレスはIBSの症状を悪化させる要因となるため、ストレス管理は重要です。リラクゼーション法や認知行動療法などは、ストレス反応を調整し、症状の緩和に繋がります。
薬物療法
IBSの薬物療法は、症状に合わせて選択されます。例えば、下痢型IBSには止瀉薬、便秘型IBSには下剤などが用いられます。また、腹痛を軽減する薬剤も存在します。
診断が難しい理由は何か?
IBSの診断は、他の消化器疾患を除外する必要があるため、複雑な場合があります。明確な検査方法がなく、主に症状に基づいて診断されることが難しさの一因です。
- 客観的な検査マーカーがない:IBSには血液検査や画像検査で特異的に診断できるマーカーがありません。
- 他の疾患との鑑別が必要:クローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患、セリアック病、大腸がんなど、IBSと似た症状を示す疾患を除外する必要があります。
- 症状の多様性:IBSの症状は個人差が大きく、腹痛、下痢、便秘など様々な症状が組み合わさって現れるため、診断を難しくしています。
治療法の選択基準とは?
IBSの治療法は、患者の症状、重症度、生活習慣、そして患者の希望を考慮して決定されます。主な選択基準は以下の通りです。
| 症状の種類 | 主な治療法 | 補足 |
|---|---|---|
| 下痢型IBS | 止瀉薬、低FODMAP食 | 水分補給も重要 |
| 便秘型IBS | 下剤、食物繊維の摂取、運動 | 十分な水分摂取が必要 |
| 混合型IBS | 下痢と便秘の両方の症状に対応する薬物療法、食事療法 | 症状に合わせて治療法を調整 |
| 腹痛が強い場合 | 鎮痙薬、抗うつ薬 | 痛みの程度に応じて薬剤を選択 |
上記以外にも、漢方薬やプロバイオティクス、鍼灸などの代替療法も検討される場合があります。どの治療法が適切かは、医師と相談しながら決定することが重要です。
まとめ
過敏性腸症候群(IBS)は、腹痛や下痢、便秘などの症状を繰り返す慢性的な疾患です。原因は未だ完全には解明されていませんが、ストレスや生活習慣、腸内環境の変化などが影響していると考えられています。
IBSの診断は、問診や身体診察、必要な場合は血液検査や便検査などを通して行われます。残念ながらIBSを根本的に治癒させる特効薬はありませんが、症状を軽減し、日常生活の質を向上させるための様々な治療法が存在します。
内科的治療では、下痢や便秘といった症状に合わせて薬が処方されます。食事療法では、食物繊維の摂取や刺激物の制限などが推奨されます。
また、ストレス管理や適度な運動、十分な睡眠といった生活習慣の改善も症状緩和に繋がります。
ご自身の症状や生活スタイルに合った治療法を見つけることが重要です。医療機関を受診し、専門医と相談しながら治療を進めていきましょう。
最後に

さとう接骨院
院長:佐藤幸博
仙台市泉区の整体 さとう接骨院は、痛みへの施術だけでなく再発予防まで、お客様一人ひとりの健康を大切にオーダーメイドで対応しています。
施術・メンタルヘルス・運動・栄養・睡眠の5本柱で、根本的な解決策を。お体の悩みやご相談はいつでもご予約・お問い合わせからどうぞ。
参考リンク:
[2]日本消化器病学会ガイドライン|過敏性腸症候群(IBS)
[3]Enck, P. et al. Irritable bowel syndrome. Nat Rev Dis Primers 2, 1–24 (2016).
-

2026年2月12日
変形性股関節症で歩けない原因は? 自宅で悪化を避けるコツ
-

2026年2月3日
椎間板ヘルニアと足のしびれの関係
-

2026年1月22日
猫背を整えたい方へ、矯正よりも大切な“体の使い方”とは
-

2026年1月16日
40代から急増する「ストレートネック肩こり」って?今こそ見直したい体のバランス
-

2026年1月9日
痛みの再発を防ぎたい方へ…産後骨盤ケアがもたらす可能性
店舗情報
-
店舗名
- さとう接骨院
-
代表
- 佐藤 幸博(さとう ゆきひろ)
-
住所
- 〒981-8003
宮城県仙台市泉区南光台3丁目19-23コーポ展1階
専用駐車場2台
地図を見る -
営業時間
- 9:00~13:00 / 15:00~21:00
詳細はこちら -
休診日
- 日・月曜日 不定休あり
-
アクセス
- 地下鉄南北線旭ヶ丘駅から車で2分
-
TEL
-
022-343-5542
施術中はお電話に出られません。
留守番電話に「お名前」「ご要件」を残してください。
こちらから折り返しご連絡させていただきます。
営業時間
さとう接骨院は 「 当日予約OK 予約優先 」 です。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00〜13:00 | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | ◯ |
| 15:00〜21:00 | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | ◯ |